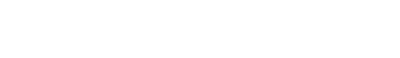「大阪芸術大学特別演奏会2024~あなたに贈る特別なコンサート~」開催 「大阪芸術大学特別演奏会2024~あなたに贈る特別なコンサート~」開催

12月5日、大阪市・中之島のフェスティバルホールで「大阪芸術大学特別演奏会2024~あなたに贈る特別なコンサート~」が開催されました。演奏学科が学びの集大成と位置付ける恒例のコンサート。今年はフォーレ作曲の「レクイエム 二短調 作品48」と、ムソルグスキー作曲の組曲「展覧会の絵」の2曲が演奏されました。
クラシックの名曲を憧れのフェスティバルホールで演奏
演奏学科では年間のカリキュラムのなかに、日々の学びを披露する数々の演奏を披露する機会が設けられています。その中でも毎年開催される「特別演奏会」は国際的なマエストロである大友直人教授の指揮のもと、プロの演奏家と共演できる貴重な機会。クラシックの演奏家がそのステージに立つことを目指す音楽の殿堂・フェスティバルホールで、これまで研鑽を積んできた成果を発表します。そんな特別な経験を積み重ねて、学生たちは演奏家として成長していきます。
2024年の「特別演奏会」では大阪芸術大学管弦楽団と、大阪芸術大学混声合唱団がフォーレ作曲の「レクイエム 二短調 作品48」と、ムソルグスキー作曲の組曲「展覧会の絵」の2曲を演奏しました。

一流ホールの舞台を踏み経験値を上げる
入念な準備の末、迎えたコンサート当日。午後から始まったリハーサルにて、ホールでの初音合わせを行いました。大友教授による細かな調整指示やオーケストラと合唱の音合わせなどが行われ、学生たちはホールの音の響き、音の届き方など会場の臨場感を肌で感じ、緊張感や高揚感が高まりました。

多彩で豊かな音色が魅力の「展覧会の絵」
客席が観客で埋まり、いよいよ本番。ホールはほぼ満席です。
流れるような美しい所作で大友教授がタクトを振ると、トランペットが「展覧会の絵」の象徴的な「プロムナード」の冒頭フレーズを高らかに奏でられ、演奏会の幕が上がりました。



ムソグスキーが10枚の絵から着想を得て作った「展覧会の絵」は会場に飾られた絵=曲を、ゆっくり歩いて回る「プロムナード」をはさみながら続く組曲。特に今回のラヴェル編曲版では各曲を豊かに表現する楽器編成の多彩さが特徴であり、管楽器が華やかに奏でます。学生たちは自分のパートを1音1音ていねいに表現し、堂々と演奏を披露しました。難曲といわれる「展覧会の絵」ですが、大友教授の導きにより一体感のあるアンサンブルで奏でていきます。
終盤はダイナミックな打楽器が活躍し、「キエフ(キーウ)の大門」ではラストを金管楽器がフォルテッシモで盛り上げるなど、フルオーケストラの壮大なスケール感が圧巻でした。

混声合唱団とソリストが歌い繋ぐ壮大な「レクイエム」
休憩をはさんで、会場にはオーケストラと大合唱団、ソリストがスタンバイ。フォーレ作曲の「レクイエム 二短調 作品48」のスタートです。「入祭文とキリエ」の始まりから祈りの言葉「主よ、永遠の安息を彼らに与えてください(レクイエム・エテルナ・ドナ・エイス…)」が合唱され、静謐な空間にハーモニーが響きます。
世界3大レクイエムのひとつに数えられるフォーレの「レクイエム」は厳かな鎮魂の思いと美しさを内包しています。今回の合唱団には入学年から回を重ねて参加している声楽科の学生から、基礎から声楽を学び始めた他学科・コースの学生まで総勢136名が参加。練習の成果を各々が全力で歌い繋ぎ、心をひとつにして美しいハーモニーを奏でました。


バリトン・三原剛演奏学科長と、ソプラノ・東野亜弥子選任講師がソリストとして加わり、思わずひきこまれる歌声や堂々とした姿で会場を魅了。プロのステージでの在り方を共演者として肌で感じた学生たちは大きな刺激を受けました。


最後の「イン・パラディスム」ではソプラノが「天使たちの合唱は聞こえ(コルス・アンジェロム・テ…)」と歌い、「永遠に安息を得るでしょう(エテルナ・ハベアス・レクイエム)」という合唱全体で結ぶ優しいフィナーレで終演を迎えました。あたたかな拍手とともに、そのおだやかな余韻がしばらくの間終演後の会場を満たしました。




「レクイエム」4曲目の「ピエ・イエズ」のソプラノソロを担当しています。1曲目からずっと学生たちががんばって紡いできた音楽のバトンを受け取り、そしてまた次へバトンを渡す。そんな気持ちで歌いました。教員として普段から知った顔ぶれの学生と一緒のステージに立つのは、見守る気持ちと、同じ演奏家として励ましあいながら作品を作りあげる気持ちの両方がありますね。今年のメンバーはとても歌声が美しく、オーケストラ合わせの時にみんなが作品に対して気持ちをひとつにして取り組んでいるのを感じ、それが自分の励みになりました。フォーレの「レクイエム」には天国に昇るような美しさを感じます。今回の特別演奏会は「あなたに贈る特別なコンサート」というテーマですので、お越しの皆様の心に届くものを、音楽を通じて感じ取っていただけていましたら、とても嬉しいです。
大学では「日本歌曲研究」という授業を担当しており、学生たちは、例えば新しい解釈の発見や、詩へのアプローチ、感情の込め方など、とても良い視点で人の演奏を捉えています。お互いの演奏を聴いて良いところを尊重しあい、意見を交わしながら相乗効果で伸びているのを感じます。そこが声楽コースの素晴らしいところです。
私も本学の出身ですが、大阪芸術大学は心から芸術を学べるところが素敵だと思います。多様な学科があるため、音楽以外にも他のあらゆる芸術と触れることができ、同じ時代の音楽や同じ時代の美術など、そのつながりを芸術全般で感じることができるのは、大きな強みであり魅力なのではないでしょうか。

「特別演奏会」はクラシックの名曲を伝統的な方法で演奏するコンサートです。今年は特に「展覧会の絵」いうトランペットが大活躍する曲なので、いっそう指導に力が入りました。トランペットは3人3管なのですが、オーディションで選抜された学生と直前まで一緒に演奏をして、「プロのオーケストラではこういう風に吹くんだよ」ということを学生に伝えました。特に曲中のピッコロトランペットのソロは難易度の高いパート。この演奏会のために練習を始めていたのでは間に合わないほど難しいものです。大阪芸術大学演奏学科では独自の取り組みで、2年生の授業のなかで、私とピッコロトランペットをデュエットするというカリキュラムを設けています。今回はそういった下地があるからこそ、この難曲を演奏することができるのではないかと思います。
満席のフェスティバルホールで演奏をするということは、プロでもなかなか得難いことなので、学生にはこの舞台での臨場感を味わってほしいですね。1年生から4年生まで毎年フェスティバルホールで違う曲を演奏する機会を重ねていくと、相当な経験になると思います。
ホール環境も反響板を閉め切って音響のよい状態にして演奏を行います。観客の皆様にもフェスティバルホールの最大限によい響きで演奏を聴いていただけると思います。また各弦楽器のトップは日本を代表するプロオーケストラから客演していただいでいます。トッププロと学生が協力して作るサウンドを楽しんでいただけたのではないでしょうか。

「特別演奏会」に出演するのは今年で3回目になります。大学に入るまでホールに立ったことがなく、フェスティバルホールのリハーサルで初めてステージに立って客席を見たときは、演奏する前なのにもかかわらず、もう感動を覚えていました。本番を迎えて客席が観客で埋まると、またリハーサルとは景色が違い、響きも変わってきて気持ちが高まりました。緊張のなかで自分がどう演奏するのか、いかに壮大な音楽を作れるかを意識して本番に臨み、歌った後は達成感に満ちて、とてつもない快感を味わいました。大阪芸術大学に入って、この舞台に立てるのは、本当にいい人生だなと思います。
私はパートがソプラノなのですが、今年の「レクイエム」では繊細な曲でいかに高音をキープするかが課題でした。しかもピアニッシモのとても線の細いフレーズを大勢で合わせるので、この統一感が一番難しかったところです。歌詞にアンジェリーとあり、エンジェル=天使という単語になります。先生から、そこをイメージするようにご指導いただき、天使が舞い降りてきたというイメージを持って演奏しました。
普段の練習ではピアノなどの鍵盤楽器で合わせていましたが、オーケストラと合わせてみると音のスケールが全く違うし、それぞれの楽器は出す音域が一緒だったとしても、少しピッチが違うなどといったこともあるのが分かってきます。そうやって得たことを本番につなげていきました。
「特別演奏会」で毎年思うのは、舞台に立つ機会はとても貴重だということ。ご指導いただいたことすべてを本番で発揮していくことが最大の学びになると思います。

今日の演奏会に向けて「展覧会の絵」の個人練習では、楽曲の技術的な完成度を高めることを徹底しました。特に「ブィドロ」の旋律ではユーフォニアムならではの豊かな音色を表現しようと音の深さや響きにこだわって練習を重ねました。この曲は揺れるようなリズムや牧歌的な雰囲気があり、牛車がゆっくり進む風景が浮かぶような曲です。テンポやリズムの揺れなど細かいニュアンスもていねいに追及し、旋律が自然に流れるようにするため、フレーズのつなぎやダイナミクスの変化にも細心の注意を払いました。
合奏練習やリハーサルでは全体のバランスの中で自分の音が他のパートとどう調和するのか確認しながら取り組みました。今後も様々な編成の演奏を体験していくと思いますが、自分の音が全体の中でどのように活きるのかを意識しながら演奏することを大切に取り組んでいきたいと思います。
1回目にこの舞台に立ったときは合唱団の一員としての参加でしたが、当時はただ先輩についていくといった感じでした。4年生になった今、この歴史あるホールで演奏することに感謝や喜びを感じると同時に責任も強く感じました。大規模な編成での演奏はプレッシャーもありますが、それ以上に一体感を生み出す楽しさを味わいたいという期待感が大きく、本番では今までに積み上げてきた集大成として臨むことができました。
振り返ると先生や先輩、後輩、同期とのつながりを持っていろんな演奏を共にできたことが一番楽しかったことです。卒業後は教職に就きながら、プレーヤーとしても演奏を続けたい気持ちがあり、楽団のオーディションやコンクールにもチャレンジしていきたいと思っています。