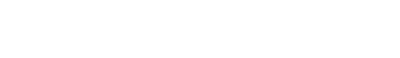アートサイエンス学科生のインタラクティブコンテンツが織りなす「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024」 アートサイエンス学科生のインタラクティブコンテンツが織りなす「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024」

大阪芸術大学アートサイエンス学科の学生たちも参加した「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 ―Go Around OSAKA―」が、あべのハルカス展望台「ハルカス300」にて2025年3月31日まで開催されています。同イベントは、株式会社ネイキッドと同学科よる共同プロジェクト。今回は、学生たち企画から制作まで携わった体験型のインタラクティブコンテンツが披露されています。

学生たちが発案、音楽をテーマに「言語の壁を越えて人と人を繋げる」
2015年に始まった、「ハルカス300」で新感覚マッピングショーが堪能できる「NAKED CITY LIGHT FANTASIA」。アートサイエンス学科は、若い才能を育むために取り組まれている「0×0=∞(ムゲンダイ)プロジェクト」の一環で同イベントに参加しています。ちなみに今回は大阪をぐるっと回るを意味する「―Go Around OSAKA―」をテーマにイベントが開かれ、大阪の名所をプロジェクションマッピングで表現。2025年に『大阪・関西万博』が実施されることもあり、大阪の名所の魅力を伝える内容になっています。


ネイキッドのディレクターでアートサイエンス学科講師の川坂翔先生の指導のもと、サイエンス学科生たちが演出企画・構成を担当したインタラクティブコンテンツを楽しめるのは、58階「天空庭園」ツインタワーです。ツインタワーに映し出される風船の絵をタッチすると本が飛び出してページがめくれ、大阪城など大阪の名所の絵が出てきます。そしてさらに映像に触れると次は楽器の絵が現れ、それに触れると音が鳴るとともにエフェクトが投影され、いろんな情景を見ることができます。たとえばバイオリンを鳴らせばランタンが幻想的に浮かび上がり、トランペットを鳴らせば花びらが舞います。一人で楽しめるのはもちろんのこと、一緒に居合わせた見知らぬ誰かと“演奏”することも可能です。

大阪は現在、『大阪・関西万博』やインバウンドの状況が表しているように、いろんな人たちが結びつく街になっています。音楽という“世界共通言語”をもってして、様々な人と一緒に体験することができるこのインタラクティブコンテンツは、“大阪の今”そのものと言えるのではないでしょうか。ちなみに同コンテンツを体験した5歳の男児に感想を聞いてみると「やってみておもしろかった。風船に触るといろいろ出てきてすごいなって思った」と驚いていました。

また、11月13日にはオープニングセレモニーと点灯式が開催されました。その席で川坂先生が「万博やその先の(大阪の)未来に希望を持っていただける体験になるはず」と期待を寄せると、アートサイエンス学科生の國重拓哉さんは「音楽は言語の壁が越えられるものだと思っています。音楽と映像を使って世界中の人を繋げる場所ができたらと思って制作しました。この作品が世界中の人を繋げ、皆さんの素敵な思い出になってほしい」とコメント。大阪芸術大学の塚本英邦副学長は「(来場者に)作品を見ていただくことで、学生たちの成長に繋がります」とこの取り組みの意義を語りました。
「NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 ―Go Around OSAKA―」は2025年3月31日まで、あべのハルカス展望台「ハルカス300」にて実施されています。

【開催概要】
イベント名:『NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2024 ―Go Around OSAKA―』
開催場所:あべのハルカス展望台「ハルカス300」(大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1−1−43)
開催期間:2024年11月13日(水)~2025年3月31日(月)
主催:CLF2024あべのハルカス実行委員会・近鉄不動産株式会社
特別協力:大阪芸術大学アートサイエンス学科
後援:公益社団法人関西経済連合会、公益財団法人大阪観光局
企画・演出・制作:株式会社ネイキッド ※詳細はハルカス300公式HPをご確認ください。
「ハルカス300」
WEB:https://www.abenoharukas-300.jp/index.html
「0×0=∞プロジェクト」


鵜飼:学生のみんなでゼロから意見を出し合って企画を作り上げていったので、それが一つの形になってとても嬉しいです。しかもオープニングセレモニー後、体験してくれる人たちがたくさんいて「作って良かった」と思いました。
上田:作るのは本当に大変でした。でもいろんな方が楽しそうにインタラクティブコンテンツに触れてくれていて、「作品を体験してもらうことって、こんなに嬉しいものなんだ」って感激しました。
泉谷:まず本の絵が映し出され、それにタッチすると物語が始まり、体験者がその世界に入り込んでいくという構想は当初からあったものでした。逆に「ピアノを置いて、それを弾いてもらう」という元々のアイデアはハードルが高いことが分かり、練り直しが求められました。そこで「さらに良いものにするのは、どういう風に変更すればいいか」と悩みました。
上田:ほかにも難しかった点は、どの程度、各自の意見や思い入れを取り入れながら一つの作品として完成に近づけていくかというところ。私は、映像に浮かび上がる楽器、建物、場所などの絵を担当しましたが、どれくらい描き込むべきかなどは学生同士でしっかり話し合う必要がありました。たとえばお花畑が出てきますが、何本くらい花を描くかはそれぞれのイメージがあったので、そういった考えをまとめていくところに難しさを感じました。
鵜飼:私はプログラミング担当でした。今回のインタラクティブコンテンツで言うと、本棚にある赤い本に触れると次の動画が表れるという展開面や、本が開き切ったらそこから楽器が出てくるエフェクトなどの制作を行いました。ただ、これまでほとんど使ったことがないソフトだったので、まずそれに慣れるのが大変で。ですので、いろいろ勉強になりました。
泉谷:自分の担当は、このインタラクティブコンテンツの体験の仕方などを案内するパネルやポスターの制作でした。作品の入口になるものなので、責任重大。ただ、どうやったらその掲示物を見てもらえるか、いろいろ模索しました。意識したのは「その日の一人目のお客様をどのように獲得するか」ということ。ガイドを目にして一人目の体験者が現れたら、その様子を見て、二人目、三人目と続いていくはず。川坂先生からは「文字で読ませるよりも、パッと見て興味を持ってもらうことが大切。作品内容、体験の仕方も掴めるデザインにしましょう」とご指導いただきました。「第一印象のデザインが大事」という言葉が印象に残っています
上田:私は、川坂先生の「いろんな人が体験しやすいコンテンツってどういうものだと思いますか」というお話が頭に残っています。先ほど、泉谷さんからもお話があったように、ピアノを設置するという当初のアイデアはやっぱり敷居が高かったと思うんです。今の形の方が体験しやすい。川坂先生のご指導は「体験しやすいコンテンツとは?」について改めて考えるきっかけになりました。
鵜飼:川坂先生はエフェクトの見せ方にも細かいこだわりを持っていらっしゃり、その視点の鋭さに「すごい」と何度も思いました。流れ星の輝きにしても、「もっとキラキラを足していこう」とか。プログラミングに関してはまた別の先生にご指導いただいたのですが、「本番前の施工ではこういうところに気をつけた方がいい」「こういうプログラミングをするときは、ここを動かしてみよう」など、より実践的なお話をたくさんお伺いすることができました。
泉谷:そんな今回のコンテンツのメッセージ性は、大阪・関西万博のテーマでもある「いのちのつながり」。それをさらに追求すると、人と人との繋がりでもあると自分は考えています。音楽を軸にしたのも、言語などを越えた繋がりが生まれて欲しいという願いがあってのこと。この社会の中で、もっと様々なコミュニケーションの形が生まれて欲しいです。
上田:特にこのインタラクティブコンテンツは、知らない人同士でも一緒に体験することができる。そういう、人と人が繋がれることの温かみみたいな雰囲気を感じ取ってもらいたいです。
鵜飼:言語の壁などを越えて、世界はもっと一体になることができるのではないでしょうか。いろんな人が繋がれるように、という願いを込めながら作りました。2025年の『大阪・関西万博』に向けて、世界中が一致団結して欲しいです。このインタラクティブコンテンツがそのきっかけの一つになってくれたら嬉しいですよね。
Photo gallery