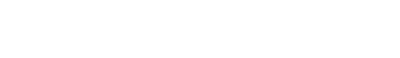舞台芸術学科 学外公演『夏町』開催 舞台芸術学科 学外公演『夏町』開催

2025年7月12日、13日の2日間、大阪芸術大学舞台芸術学科の2025年度学外公演『夏町』が大阪市中央区のCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて上演されました。同作には、舞台芸術学科の演技演出コース、ミュージカルコース、舞踊コース、ポピュラーダンスコース、舞台美術コース、舞台音響効果コース、舞台照明コースに在籍する3年生が全員参加し総勢150名以上で大舞台を作り上げました。

150名以上の学生が参加した熱量たっぷりの舞台
舞台人をめざす学生たちにとって貴重な経験になるほか、学内公演ではなかなか味わえない緊張感が学生たちの成長を後押しする、舞台芸術学科の学外公演。近年の学外公演は有志の学生たちが参加していましたが、今回は授業課題として全コースの3年生全員が取り組むものに。さらに芸術監督を山本健翔学科長、作・演出を内藤裕敬先生、作曲を中村康治先生、歌唱指導を村井幹子先生、振付を堀内充先生と栗原めぐみ先生が担当するなど、各学科で教鞭を執る先生方が勢揃いしました。

『夏町』は、内藤先生の書き下ろし作品。豪雨災害で流木やゴミに埋め尽くされた入江を前に途方に暮れる人々、そして社会の現実を突きつけられて、もがきながら毎日を送るかつての夏町の住人たちの葛藤と再生の物語です。「夏はもう、ダメかもしれない」「どう考えても子どもの頃の夏とは違うもんね」といった台詞があらわしているように、地球環境や社会のいろんな変化と、小さいときに抱いていた理想や夢が大人になるにつれて徐々に失われてしまう現実のほろ苦さが重ねて描かれていました。
そんな同作で圧巻だったのが、出演者が約100名を数えたところ。その全員が登場する場面もありました。特に印象的だったのが、夏町の海辺で音楽フェスが開催されて大勢が集まる物語序盤。サーフミュージックが鳴り響いてロックコンサートのような盛り上がりが演じられ、さらにバレエ音楽の要素を取り入れたリズムへと転調していき、舞踊コースの学生たちが登場してバレエを踊るなどして舞台上を賑わせました。またポピュラーダンスコースの学生たちもエキサイティングなストリートダンスを披露。多種多様な演技、ダンス、音楽で構成されました。




大勢の出演者が登場する舞台を支えた、スタッフワークも見逃せませんでした。夏町の海岸沿いのセットなどを手がけた舞台美術コース、歌やダンスがふんだんに出てくる同作のサウンド面を担った舞台音響効果コース、華やかな場面から絶望感漂う場面までさまざまな雰囲気を創出した舞台照明コース。各コースの学生たちの手によって、『夏町』が作り上げられたと言えます。



未来のことは誰も分かりません。そして誰だって必ず、人生の中で躓くことはあります。「私たちはこれからどのように生きるか」というメッセージが感じられる『夏町』。その物語の中の役を演じ、そして制作した学生たちは、きっとまた一回り大きく成長できたのではないでしょうか。



『夏町』は、書き下ろしの作品の初演だったのです。それはつまり、まだなにも決まっていないところから物事を生み出していかなくてはならないということ。舞台美術は、作家が書いた脚本をもらってすぐに、どのパートより早く創作作業に取り掛からなければなりません。私たちが空間を創って、役者の立ち稽古が始まり、照明プランが生まれます。実際に今回、舞台美術コースの学生は、内藤先生が一旦書いた台本冒頭をもとにイメージを膨らませ、3月春休み中にラフスケッチという舞台セットのデザイン画(第1プラン)を描く作業に取り掛かりました。また舞台美術は「調べる芸術」とも言われています。安易に誤魔化すとパッと見てバレます。ですので、台本を読んだ上でちゃんと解釈を深め、わからないことは全て調べるという作業が必要です。その上で学生たちには「瓦礫などが漂流してきた海岸」「町のジオラマ」「野戦病院」「海の家」のデザインを提出してもらいましたが、ほぼ全員が全課題を提出してくれました。力作ばかりでした。学生全員が『夏町』に相当深く向き合っている印象を受けました。しかし、膨大な量のラフスケッチも採用されるのはそれぞれ一つだけ。それでも、落選して心が折れている場合ではないことはみんな心得ています。なぜなら1回生のときから常に授業において自分の作品に関するプレゼンをやり続け、なにが足りないのか、コンペに選ばれる人はどこが優れているのかなど、たくさんのことを学び吸収しているからです。そうやって切磋琢磨しながら力をつけていっています。そんな中『夏町』では、別のコースの学生と連携するなど普段より多くの人との作業を経験しました。みんな、お互いにリスペクトを持ちながら仕事をしていました。そうやってコミュニケーションの取り方を経験できるのも学外公演ならでは。その点で非常に貴重な時間を送れたのではないでしょうか。

『夏町』は、自分と重なる部分がたくさんあった物語でした。20代は、自分への期待が大きく、夢はいくらでも見ることができる。しかしこの物語には、うまくいかなかった人たちが登場します。「こうなりたい」と思っていても、叶わなかったという現実が感じられます。稽古中も内藤先生から「思い通りにならないことは多いんだ」とおっしゃっていました。私たちは今、20歳前後。「十代が終わってしまった」という感覚があり、これから20代をどのように生きていくのか考えていたところなので、心に刺さるものがありました。そんな『夏町』の本番で意識していたのは、その状況をどういう風に遊ぶかということ。内藤先生からも稽古中、「その芝居は自分があらかじめ考えてきたことを披露しているだけであって、状況で遊んでいない」とよくお話されていました。ですので毎公演、その場で実感したことを素直に出していました。台本上の動きや台詞はきっちり守りつつ、すべての公演で全然違う反応をしていたと思います。私はそうやって演技をしている時間が一番好き。30代、40代になっても演技をやっている自分を見てみたい。今後、なにがあっても俳優は続けていきたいです。

舞踊コースでは普段、自分たちの公演ではバレエを踊っているので、お芝居は新鮮な気持ちがありました。私は看護師役で台詞も少しいただきましたが、最初はしっかり声が出せませんでした。そんなとき、内藤先生が「前学科長の浜畑賢吉先生は、ダンサーは体幹がしっかりしているから、いい声が出せるものだと言っていたんだよ。僕もそう思うから、みんななら絶対にできる」とおっしゃってくださったんです。それまで、台詞を任された重圧に押しつぶされそうになっていましたが、内藤先生の言葉を聞いて「やり切ろう」と前向きになれました。また、バレエのシーンでは文学的に踊ることを意識しました。「悲しさは、美しさから出るときもある」とアドバイスをいただき、看護師役として、やるせない気持ちを抱いたり、ケガをした人たちを助けるために自分はなにができるのかを考えたりしながら踊りました。一方で、お芝居の中でバレエが浮いて見えないようにすることも意識し、表現しました。今回の経験も生かし、バレエに携わるお仕事をめざしたいです。バレエを教える先生になる方も多いですし、そういう進路に興味があります。これからも踊り続けたいと思っています。

私は『夏町』で主に、芝居や状況に合わせて音楽を出すオペレーターを担当しました。どのような場面で、どんな風に音楽を出すのか、ベースは事前にできています。「この場面では音量を上げる」「こういう風に音を出したら、この場面はもっと生きる」とプランを立てています。でも本番では役者の演技で、事前に考えていたことも変化します。公演ごとに役者の空気感や間合いが微妙に異なりますから、音出しもどれくらい間をためるか、もしくは早めるか変わってきます。そのため、役者と一緒に演技をする心意気で毎回やっています。「一緒に演技をする」というのは裏方としてすごく難しいこと。でも、それがおもしろさでもあります。そのためには台本を読み込み、演出家の意図や役者への指導内容にも目を向けながら、作品のメッセージを解釈する作業をしっかりやります。それをやらないと一緒に演技ができません。また、舞台で流れる音楽もどういう受け取り方ができるか考えなければいけません。普段から作品の解釈をした上でのイメージトレーニングは欠かせません。そういう音響の仕事が楽しくてたまりませんし、将来はその道へ進みたい。特に舞台などのナマモノが好き。その瞬間でしか感じられない空気を、音響スタッフとして表現し続けたいです。