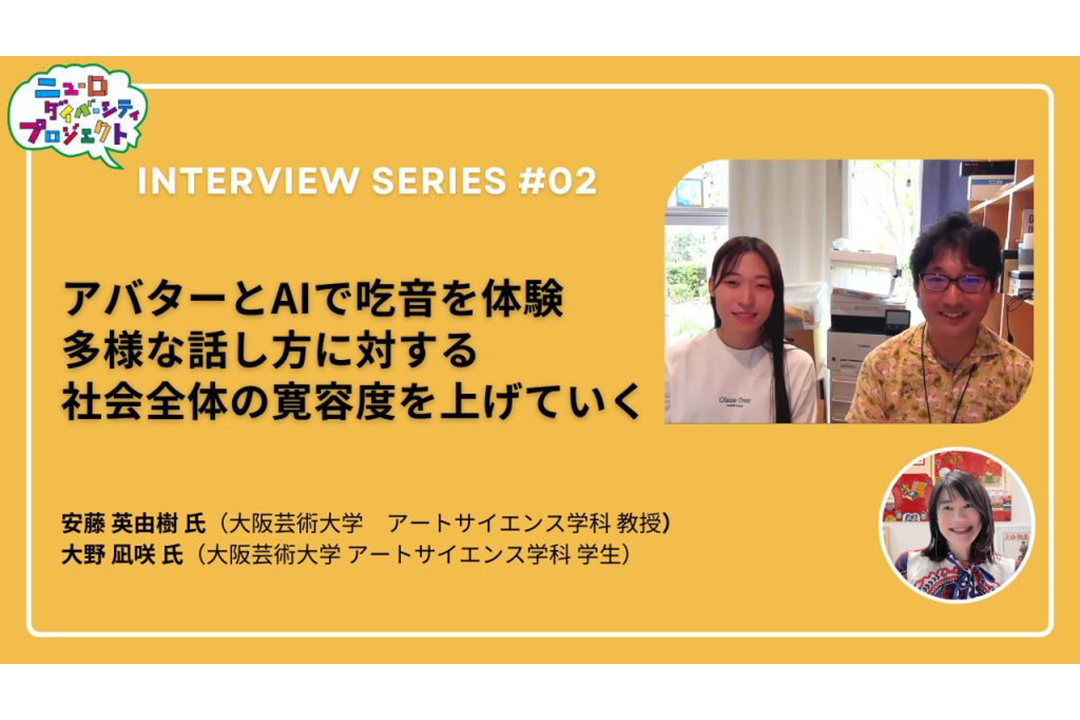2024年9月4~8日にオーストリア・リンツ市で開催された、アート・テクノロジー・社会の交差点を探求する世界最大のフェス「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」に展示しました。アルスエレクトロニカとはアルス・エレクトロニカは、1979年にオーストリア・リンツ市で設立された文化・研究機関です。アート、テクノロジー、社会を融合させた革新的な活動を行っており、毎年「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」を開催し、世界中のメディアアーティストや研究者が集まります。フェスティバルでは、先端技術と表現が融合した作品が披露されます。また、国際的な賞「プリ・アルス・エレクトロニカ」を主催し、優れた作品を表彰します。教育施設のアルス・エレクトロニカ・センターや、研究開発を行うフューチャーラボも運営し、未来社会に向けた取り組みを進めています。2024年のテーマは「HOPE – who will turn the tide(希望 – 誰が潮目を変えるのか)」です。このテーマは、変動する世界の中で希望を見出し、未来に向けた変化を導く力を問うものです。